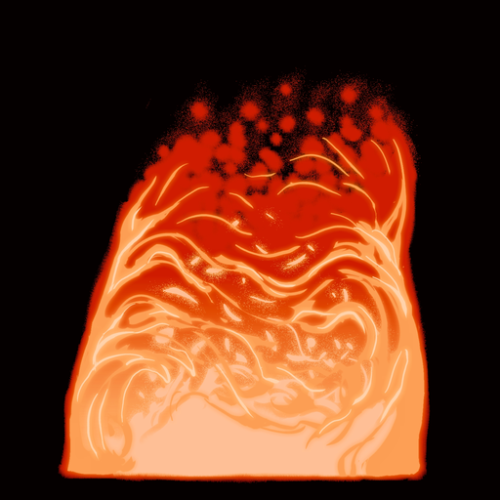
――……ブウ――――ウン、ンン―――ウウン…………。
私がはじめに思ったのは、蜜蜂が女王のために忙しなく飛び回っているのだろうかということだった。しかし、よくよく聞いてみると、どこか遠くの方でボンボン時計が響く音のように感じられた。微睡みながら遠く近く明滅するその音を聞いている内に、全く違う音が耳の奥に届き始めた。ピチャリ、水音だ、どこからか垂れ落ちる粘り気の強い水の音……ピチャリ、ピチャリ。不審に思ってそちらの方を意識しても、2つの音がどこから響くのか分からなかったが、次第にそのさらに奥の方でドクリドクリという音が重なっていることにも気がついた。それは両の掌で耳をしっかりとふさいだ時、耳元で脈が強く打つ音に似ていた。
「……もし?」
私は目を開けた。薄暗い中、荒々しく削り出された石造りの壁が見える。
「ねえ……」
異様なほどにはっきりと聞こえた女の声に、私は肝を潰すかと思った。
「もし、起きていらっしゃる? ねえ……起きていらっしゃるなら、返事をして」
その声は、壁の向こうから、そっと呼びかけてくる。不安に震える声はすがるように呼び続けている。
「ねえ、起きて下さい」
「誰ですか?」
「ああ、その声は……」
女の声は今度は感動に打ち震えた。そこで私はふと我に返った。そもそもこの女は、一体誰なんだ? と。
ぐるりと見渡すと、4畳ほどの広さを持つ石造りの無骨な部屋だったが、確かに、そこは見知らぬ個室であった。寝かされていたベッドと、そして、枕側の壁に1つだけの扉があり、目線の高さに格子のついたのぞき穴と、足元に長方形の穴が開いている。ぼんやりと部屋の内が照らされる程度に廊下からランプの灯りが漏れてきている。
ここはまさか、監獄だろうか?
何もないただそれだけの部屋に、ひたひたと女の声が染み入ってくる。
目の前の壁も覚えがない、女の声に覚えもない、――自分のことも。自分の名前、ここで何をしていたか、思い出そうとしても思い出せない。
私はベッドから飛び起きた。寝かされていた粗末なベッドが軋み、シーツの擦れる音がやけに大きく響く。あれほどしっかりと聞こえていたはずのブウウンだのピチャリだの、ドクリドクリのそれらはすっかりと鳴りを潜めていた。
一体ここはどこだ。なぜ私は一人きりこんな見知らぬ部屋に寝ているのだ、いくら考えても何も思い浮かばないというのに、女はこちらの答えも待たずにしきりに呼びかけ続けている。
「起きて下さい、ねえ、起きて」
私は落ち着かず、そわそわと腰を浮かせた。石造り壁にすっかり冷やされた空気のせいで、全身に鳥肌が立つ。寒い。身を守るように体をさすっていると、不意に指先に妙な感触が触れた。頸の後ろに縫合された切開痕らしき感触がある。こんなところを怪我していたのだろうか……。
「――あなた、目を覚ましたのね?」
あなた。愛情深く呼ばれた声に、私の胸に湧きあがったのは純然たる恐怖だった。
こんな訳も分からない場所で、自分が誰だか分かりもしないまま、知りもしない女に縋るように呼びかけられて、まともでいられるだろうか。
「ねえ、助けて、助けて下さい。もうずぅっとこのままじゃないですか。私もあなたもこうして閉じ込められて、こんなの……」
「あ、あなたは私を知っているのですか?」
あまりの恐ろしさに、私は彼女の言葉を遮った。
「ここはどこですか! あなたは誰だ! どうして私はここにいるんだ! あなたは、私を知っているんだろう!?」
部屋中にぐわんぐわんと私の叫び声が響いた。
何も。そうだ、私は何も知らない。この部屋も、この部屋にいる自分のことも、そして、この女のことも。愛おし気に祈るように縋られてもどうすることも出来ない。何も知らないのだ。何をしてやることなど、出来ようはずもない。
女は答えなかった。
「そんなことをどうして……」
代わりにまた、震える声で女は言った。その声は泣いてしまいそうだったが、泣きたいのはむしろ私の方だった。助けて欲しいのは、私の方だ。君こそが、私を助けてはくれまいか。
「やめてくれ! なんなんだ!」
喉が裂けんばかりに強く私は声を張り上げて叫んだ。壁の向こうの女は黙り込んでいるのか、息遣いすら聞こえなくなった。それと同時に足音が慌てた様子でこちらに駆け寄ってくる。扉の覗き窓から、骸骨のように痩せて、頬骨の浮いたぎょろぎょろとした目ん玉が覗き込んできた。
「ば、化け物……!?」
「――……あ、あぁ……! は、博士、博士が……。ヴァ、ヴァルター博士……ッ!」
耳をつんざくほどの悲鳴が廊下に反響した。私の姿を認めたその人影の、跳ね返るように扉の前を離れ、駆けていく足音だけが残された。去り際、足元の穴から白衣の裾らしきものが見えた気がした。看護婦だろうか……?
ここは監獄ではないのか? 看護婦の姿が見える直前にあの女が黙ったのは、看護婦を恐れてのことではないだろうか。私はそう思い立って、ぶるりと身を震わせた。壁の向こうにいて姿も見えない私に向かって声をかけてきたあの女は、とても正気とは思えなかった。だが、それを言えば、私自身とて、どれだけまともと言えるだろうか。
隣の女は狂っている……同じように狂ってしまった私は、薬漬けにされて、その影響で記憶を失い、こうして独房に拘束されているのではないか? そうして、この隣の女のように、同じように記憶や自身を失った者たちと共に、放置されてしまっているのではないか?
――もしここが精神病院であるならば、考えるだに恐ろしいが、私は二度と出られないのではないか。記憶がないだけで私は全く狂っていない、と思い込んでいるだけで、記憶を失っていることがすでに重大な症状なのかもしれない、とも言える。誰かが、私を精神病院に送り込んだのだろうか……そんな怖ろしいことを考える人間が身近にいたということか……。そうでなければ自ら望んで、この死ぬまで気狂いたちと過ごし己も狂っていくだけの地獄に入ろうものか。
女は今や完全に沈黙している、部屋の向こうで私の行動を窺っているのか、もう別のことに関心が向かったのか。それすらも分からない。
私は急に自身を取り巻く何もかもが恐ろしくなって、カビ臭い布団にくるまり耳をふさいで部屋の隅にうずくまった。
すると、パタパタと遠くからやってくる足音がふたつ、近づいてくるのを耳にした。
骸骨じみた人相の看護婦が、のぞき窓から私を再び見た。すぐに開錠される音がし、ひょろりと背ばかりが高い男が目に飛び込んできた。ふたりとも強張った顔で部屋を覗き込むと頷き合って部屋に入ってきた。
「誰だ……あんたたちは……」
手負いの獣のように怯えた私を見て一瞬だけ目を丸くしたものの、男は恭しく頭を下げた。
「ヴァルターと申します、あなたのことを一切任されています」
男はクマの浮かんだ瓜実顔で、さながら白いガウンを羽織った死神か。目や鼻、口はそれぞれ端正に整っているのに、どうしてだか顔の中で並んだ様子が不均衡に感ぜられる不気味さがある。
男は部屋の隅にそのまますっかりと納まりきってしまった。押し黙り私の様子を観察するように見つめ、突っ立ったまま置物のように動こうとしない。
たまりかね、私は口を開いた。
「あの……ここは」
「申し遅れましたね。ところであなたは私のことを覚えておいでですか?」
男は私に笑いかけたが、やはり死神や幽鬼の類にしか見えなかった。
「……あなたは医者ですか」
「医者といえば医者ですが、少し違います」
「わ、私は何も覚えていないんです、この部屋も、あなたも、隣の部屋の女性も、その看護婦も。ここはどこですか! それに、私は……なぜ、どうしてここに……私こそ、誰なのですか」
ヴァルター博士の眉がくっと寄った。左右の壁にそれぞれ軽く目をやると、入口側に立った看護婦に目配せした。看護婦は心得たように頷き退室する。
「……隣の、部屋? 本当に隣の部屋に女性が?」
「ええ、間違いなく。その声で目が覚めたんですから」
「ふうむ……」
私という存在は人間の形をしているものの中の空虚な洞のようなものだった。何もかも分からず、隣の女が静かになったことだけを安心している。
あの女は呼びかけてきたくせにまともに質問に答えなかった――彼女は言った、閉じ込められていると。それも、ずっと。
ふと思い当たった可能性にぶるりと震え上がると、目の前で作り笑いじみた表情を浮かべていた男は、酷く残念そうに首を振った。
「私はヴァルター、博士と呼ばれています。あなたとは浅からぬ縁がありますが、思い出せないようですね」
「本当に私を知っているのなら教えてください!」
「残念です、非常に残念……」
退出していた看護婦が戻り、ヴァルター博士と目を合わせると何も言わず首を振った。ヴァルター博士は一度だけ頷き、また私に向き直る。
「具合はいかがですか? 診察させていただいても?」
「……彼女は本当に看護婦か?」
「…ええ」
私はヴァルター博士のその言葉を信用することにした。
先ほど悲鳴を上げた目ん玉をぎょろぎょろさせた看護婦は、私に小さく素っ気ない会釈だけしてから手の差し伸べた。
私の舌を引っ張り出し、瞼の色を見、そして脈を図った。その手つきは明らかに手慣れていて、その技術は疑いようがないようだった。
「健康状態は良さそうですね……ただ、改めて伺いますが、本当に記憶だけが戻っていらっしゃらないと……?」
「そう言っているじゃないですか……」
「君、立たせて差し上げなさい。まだ足が萎えているだろうから」
ヴァルター博士は悲しそうに首を振りながら、部屋から出ていった。どうしたものか分からず戸惑っていた私だが、看護婦の手を借り立つことができた。こんな細い体のどこにこの力があるのか。私はよろよろと彼女に引っ張られ、ヴァルター博士のあとに続いた。
白い廊下の両脇には、私のいた部屋と同じ形の扉が左右2つずつある。女性の声がしたはずの隣室は、扉が開け放たれたまま、空室になっていた。
そうして連れてこられたのは、書類や筆記用具、薬瓶などが乱雑に積まれ、どこか古書独特の黴臭い匂いの充満した部屋だった。ヴァルター博士は部屋に入り、すぐに机の上のランタンに火を入れた。
柔らかく暖かな光が部屋を照らす。
天鵞絨のすり切れた赤い椅子に、その長細い体を落ち着けると、私にも椅子をすすめた。返事を待たずに看護婦は私をそこに丁重に座らせる。
「――ありがとう。もう結構」
ヴァルター博士はそう言うと頷きながら手を払い、看護婦に退出を命じた。
看護婦は何度か繰り返し、私の様子を一瞬窺ったのちに、またきゅっと口を結び、一礼して去っていった。すっかり足音がしなくなってから、ヴァルター博士は私の顔をまじまじと見た。
「どうです、落ち着きましたか」
「無茶を言わないでいただきたい。記憶もなく、医者であるあなたからもまだ何の説明もない……看護婦は確かにいるようですが……。ここはどこなんです? どうして何も説明してくれないんですか!?」
「ここは監視所です」
「監視? 私を?」
「いいえ、そうではありません。ひとまず、順を追って説明させてください。全てを一度にお話しても、混乱してしまうだけでしょう。あなたがいた部屋は訳あって施設内に設けていた独房で、あなたはそこで看護されていました」
「……ここには、私以外にも患者がいるんですか?」
ずっと同じ表情だったヴァルター博士が、少しだけ驚いたように表情を変えた。
「何か思い出すことでもありましたか」
「そうではなくて、隣の部屋にいたあの女性は一体誰ですか? 私は病気なんですか?」
「…先ほどもそのような事を仰られていましたが、隣の部屋は空室ですよ。あなたも見たはずです」
「ですが……私は確かに声を聞いたんです」
ただ、ヴァルター博士の言う通り、扉の開いた隣室には人の気配すらなかったことを、自分でも確認していた。
「患者は今はあなたしかいません」
ヴァルター博士は真剣そのものだった。
「確かに自分の名前も、どうしてここにいるかも分かりません。ですが、女性に声をかけられて目が覚めました。私に呼びかける声がしたことは間違いないんです!」
「落ち着いてください。あなたは調査中の事故から、今日まで寝ていたんです」
「事故? 調査?」
「この監視所は、誓ってあなたを監視するものではありません。ここは『異界』の監視所です」
「異界……?」
ヴァルター博士のじぃっと見つめる視線に、じわりと汗をかく。
異界。異界? ぐるぐると考え込む私に構うことなく、つぶさに観察したまま、ヴァルター博士は言葉を続けた。
「あなたは、この監視所の責任者でした。最初の、ですが。」
「私が? この、私が?」
「ええ、あなたはここで異界の観測を行う研究チーム、監視団の一員でした。数名を率いて、その崇高なる任務をこなしていたのです。……ただ、そうですね、やむにやまれる事情があり、異界にも自ら踏み込まれ……なんとか戻っていらっしゃいましたが、今日まで目を覚ますことはなく」
「異界とはなんです?」
「それが分からないので、異界と申し上げているのですよ。いわば、それを明らかにするための監視所であり、我々はその監視団のメンバーだったのです」
「異界を、監視……」
そうは言われてみても、何度私の心に尋ねても、そこには何も刻み込まれていなかった。異界のいの字も浮かばない。
「門を覚えておいでですか?」
「門というと、家の前にある、あの門ですか?」
「そうではありませんが… そうですか……」
ヴァルター博士は目を伏せて、深く長いため息を吐いた。
「では、あなたの隊にいた誰かでも思い出せませんか。あなたの大切な方もご一緒でしたが」
「大切な?」
ヴァルター博士の問いかけに、私はしばらく呆然とした。あの愛おしげに語りかけてきた女性の声の調子……まさか、あの声の主が『大切な人』だったのではないだろうか。
「それは、大切な人とは……? どうしてその人はいないのですか?」
「名前も思い出せませんか。あなた自身の名前もそうですが、大切な人の名前は思い出せそうではありませんか? 試しに思いつく名前をそらんじてみてはどうでしょう」
私はヴァルター博士の言うとおりに、思いついた名前を男女問わずに口にした。ぶつぶつ唱えてもつっかかることはなく、名前が増えれば増える度、不安ばかりがいや増しに募っていく。
「異界内の調査からは、あなたとマティアス博士以外の調査員が帰還しませんでした。あなたの大事な方であるモニカも」
「モニカ……? それは妹ですか? 母、それとも……」
「この調査が終わったら結婚するつもりだったとか」
その答えは私を震えさせた。それほど大切な人がいなくなったことをこんなにすっかり忘れ去るのか! あるいはそれほどまでに、異界の調査は恐るべきものであったのだろうか。
しかしまた、喉の奥に言いようもない違和感が残った。その人との思い出も、失った事すらも思い出す事ができないとき、人はその人を悼み、悲しむべきなのだろうか。
「この部屋も、あなたがずっと使っていた部屋です。今は私が使わせていただいているので、多少様変わりしているとことはありますが、何か目に付くものはありますか?」
その言葉が再び私を震えさせる。ここに、ずっと?部屋に踏み入った時でさえ、何かしらの感慨を覚える事もなかった。恐る恐る部屋中を眺め回し、落胆に肩を落としながら私は力なく首を振った。
「何も……何も分かりません。自分の名前も、この場所も……」
ちっぽけな虫けらのように感じる。己の存在の耐えられない空虚さに私は身じろぎした。
ふむ、と小さく頷きながら、ヴァルター博士は傍らから、ひとつの冊子を取り上げた。布張りにされたその冊子を私に差し出す。
表紙には金箔押しで『赤子の視る夢』と書かれている。小説か何かだろうか。とにかく、覚えはなかった。
「これを少し読んでいただけませんか?」
唐突な申し出ではあったが、私にはそれを拒む理由さえなかった。あるいはそれが、私の過去を記したものであるのではないか、とも思った。私は惨めな気持ちのまま、黙ってその冊子を受け取り、膝の上で開いた。

赤子の視る夢
異界の科学的考察
序文
我々にとって異界という存在が身近かつ脅威であったという論拠は挙げればキリがなく、この世界と異なる世界――異界が存在することは周知の事実である。ただ、今回発見されたロルコール村山間の門とその先に見出される異界は、通常これまでに見られた門あるいは異界とは異質なものである。従来の魔術師達が召喚を命じ応じる異界、あるいは足を踏み入れる機会を持つ異界とは全く別の、我々人類未踏未確認の新たなる異界へと繋がる門であると確信するに至った。私はこれまでに『未確認異界』の存在や脅威を考え、研究してきた。その知見を大いに活かし、この門のもたらす恩恵あるいは脅威を明白なものにする目的で、我々は実地調査を命じられる運びとなった。
ロルコール村での異変は連続多発した行方不明並びに不審死事件に端を発する。一連の事件や門の調査を通し、判明したことを以下に記す。
- 門の与える影響には精神的な発狂などを来す他、ほとんどの場合最終的には被害者の肉体は腐敗あるいは崩壊に似た奇妙な身体症状を呈す。
- 外見上、存命中の被害者と通常の人間の区別はつかない。実の親でも判別は不可能だった。ただ、幻覚や衝動的な行動、本来ならば脅威として忌避されるはずの未確認異界へと他の人間を招こうとするなどの異常行動が見られる。また、死亡した場合、その全身が崩壊しておぞましい肉片に変じたり、あるいはそうした崩壊が見られない検体においても、死後解剖によって首筋からそれと似た小さな肉片が摘出されている。
- 死後全身崩壊が起こらなかった被害者は、1例の例外もなく解剖によって首筋から肉片が見つかっている。この共通点はひとつの仮説を示している――未確認異界への接触により、その異界に存在する者に『何か』を植えつけられ、それが身体あるいは精神異常の原因となる。
- この全身がおぞましい肉片となる者は『完全な個体』であり、本来は小さな肉片が残るのみで見分けのつかない者が『不完全な個体』と考えられる。つまり、正体不明のこの肉片への”変異”が進行し、やがて完全な個体となる。
- その変異をもたらす”何か”を『卵』、植え付けられた犠牲者を『赤子』、それを植えつける存在を『乳母』とこの論文では呼称する。乳母に選ばれ『卵』を植え付けられた人間はやがて怪物となる。その際、宿主の人間の記憶を何らかの手段(『夢』と呼称する)で読みとり、人間の世界に溶け込み成り代わる。次の卵の宿主を乳母のところへ導くことで、さらに犠牲者を増やすことを目的としていると考えられる。

額にジワリと浮いた汗を拭いながら、私は冊子を閉じた。冊子を閉じる音と、私のため息が同時に響いた。
「どうですか?」
ヴァルター博士が私に穏やかに呼びかけた。
「え、ええ……」
ブウウウンとまた低い音が聞こえる。この監視所のどこかで、また時計の鐘が鳴り響いているのだろうか。
私は冊子から顔を上げた。
「この『赤子の視る夢』というのは……」
「マティアス博士という名前に聞き覚えは?」
私はまた、首を振ることしかできなかった。
「それは、マティアス博士の書かれた異界に関する論文に、博士ご自身がつけた題です。これに記されている山村の不審死事件を調査するためにあなたは派遣されました。はじめこそ、何かたちの悪い伝染病かもしれないということでしたが」
「分かりません……こんな恐ろしい事件に私は関わっていたのですか……?」
私が怯えながら尋ねても、ヴァルター博士はただただじっと私の指一本の些細な動きでも見過ごすまいと見つめているだけだ。
――外見上、被害者と通常の人間の区別はつかない。
手元の冊子から、この言葉が浮かび上がって見え、ぎょっとした。
まさか。
耳を閉じたかのように、自身の鼓動音がまた強く頭の中でドクリドクリと鳴り響いている。
まさか。
自分の首筋にある縫合の痕に指を這わせる。そこには異物感などは何もなかった。私自身、何かを植えられていたとして、自分でその事を自覚できるだろうか。
親でも判ずることが出来ないという赤子……自分のことを思い出せぬ身の私が、間違いなく人間であり、私という個人だと、胸を張れるだろうか。
まさか。この私が……自分の指先がグズグズに腐った肉片なのではないかと、恐る恐る手をランタンにかざしたが、血潮が透けただけだった。ただ、それがどれだけの安心になろうか……私が命を落とすそのときまで、この指先から身体の全てまでが肉片に変じない保証はどこにもないのだから。
~つづく~
原作: ohNussy
著作: 森きいこ
「ショートストーリー」は、Buriedbornesの本編で語られる事のない物語を補完するためのゲーム外コンテンツです。「ショートストーリー」で、よりBuriedbornesの世界を楽しんでいただけましたら幸い
です。




