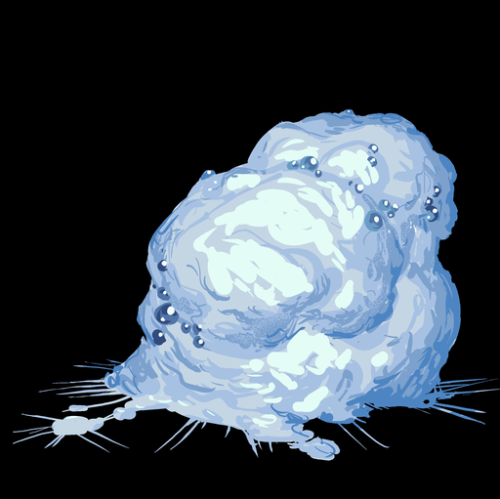
冬、雪深い季節に、エレドスティ山地に足を踏み入れる者は少ない。
麓に住む数人の狩人が、備蓄が尽きてやむを得ず食料を求めて入山するばかりである。
仮に入山しようとする者がいたとしても、無関係の者の多くは、そうした者達を自殺志願者として扱う。
そのため、道案内など頼まれようものなら、道連れを恐れ、誰も首を縦に振る事はない。
しかし、今回だけは、事情が違った。
多くの無知蒙昧な麓の村民達にとって、屍術師の集団などなおさら忌避すべき余所者だ。
私自身でさえ、置かれた状況の変化がなければ、そうした連中と同じように門戸を閉ざし、その冒涜者達と直接まみえることさえもなかっただろう。
しかし今、私は彼らと旅程を共にし、馬車に揺られながら、エレドスティの中腹へと向かっている。
村から半日ほどかけて、馬車は間もなく野営予定地に到着する。
幌の端を軽く捲って外を覗き込むと、麓の村が放つ灯光が白い斜面の先にぼんやりと小さく視界に映る。
あれは、滅びゆくものが放つ、最後の光だ。
私はその村の姿を遠目に見るごとに、死にゆくものを看取るような気持ちを抱いていた。
私が、妻や、老いた両親や、幼い我が子を看取ったときと同じように。
この冬の寒波は一層強く、そして何より、山が牙を剥いたのだ。
それは、自然の力強さだとか、野生動物の活動だとか、そういったものとは性質の異なる、この世のものとは思えない悍ましいものだった。
被害者の多くは、暗く虹色に発光するタール状の痕跡だけを残し、腕一本さえも帰ってくる事はなかった。
被害者こそ数人に留まったが、村の狩人達は完全に萎縮してしまった。
被害者達の末路を知る者はいないのだ。
誰だって、得体のしれない怪物に連れ去られ、どんな悲劇が待ち受けているのかわからない魔境に足を踏み入れるくらいなら、餓死した方がマシと考える。
私自身も、気持ちは同じだった。
狩人のワットと言えば、村で知らぬ者もいないほどの狩りの名手と謳われたものだ。
それが今では、屍術師達の手先に成り下がった、とでも言うのか。
それでも、良いじゃないか。
どうでも良かったのだ。
家族は皆、餓えて死んだ。
あとは私も後を追って、皆の待つ場所へ逝くだけだったのだ。
そこに、彼らがやってきた。
他の村民には門前払いされたそうだが、私はそうはしなかった。
相手が誰であろうと、誰が家に来ようとも、もう、どうでも良かったのだから。
この連中が帰ったら、その後自死しようか、とまで思っていたのだ。
しかし、悪魔は囁き、私は応えた。
エレドスティ山地の案内料は、今どき珍しい、金貨で支払われた。
これだけの金貨があれば、都市廃墟の闇市場に行けば、幾らでも食料を買える。
死なずに済む、生きられる。
そう思ったとき、はじめて死ぬ事が恐ろしくなったのだ。
村民達はきっと私を、家族を見殺しにした死にぞこないとして軽蔑するだろう。
金も分けずに、一人で屍術師達に取り入って生き延びた、裏切り者。
なんとでも言えば良い、それでも私は生きたいのだ。
そして連中は、この冬を越えられず、一人の例外もなく息絶えるだろう。
だから、あの灯光は、死にゆくものの光なのだ。

私だけが、彼らの訪問を迎えたのだから、私だけが、生き延びる資格を有していたのだ。
屍術師達は、馬車を引き連れて現れた。
手綱を引き、二頭の馬を巧みに操るのは、意外にも女性だった。
はじめ御者席に座る彼女を遠目に見たときに、巨漢と見紛うほどの長身であった。
肩口で切り揃えられた銀髪の先が、黒いコートに縫い付けられたフードのファーに埋もれていた。
雪のように白い肌と切れ長の瞳が、妻に似ていると思った。
名を名乗り挨拶した私を一瞥し、彼女はそっぽを向いてしまった。
仲間との会話から、彼女はアリーセと名乗る事がわかった。
直接門戸に立ち交渉を持ちかけてきた男は、ライツと名乗った。
彼に対して抱いた第一印象は、”普通”だった。
特徴のない顔、伸ばし放題の髪をくくり、肩に垂らしていた。
ヒゲだけは丁寧に剃刀を当てているようだったが、それが逆に無個性さを強調しているようにも思えた。
鈍色のローブの中は見えなかったが、この寒い中でも厚着はしていないようだった。
交渉中も始終抑揚のない発声で、事実のみを淡々と述べていた事が印象的だった。
一方で、交渉が成立し、馬車から飛び降りてきた男は、逆の印象を与える人物だった。
男はジョゼフと名乗り、狼狽する私の掌を強引につかみ、白い歯を覗かせながら握った手を雑に振った。
短く刈り込まれ撫でつけられた髪と猟犬のような端正な容貌は、都会の社交界で幅を利かせていた男前の紳士達とやらを思わせた。
体のシルエットに沿ったハンター用のジャケットとキャップを着こなし、身振り手振りから気取りが感ぜられて、人に見られる事を強く意識しているだろう事が、余計にライツとの違いを際立たせたように思う。
馬車にはこの3人が乗り込んでいた。
そして、馬車の荷台の脇に積まれた、曰く有りげな大袋、5つ…
彼らが何の集団なのかを知っていれば、その袋が何を入れたものなのか、容易に想像がつく。
とはいえ、私はそのことを口に出す事はなかった。
袋は完全に密封されているようだったし、雪深く積もる山中においては、匂いが漂う事もないのだろう。
私は、荷台に設えられた簡易椅子の、一番外側に座していた。
その隣で、ライツが姿勢良く揺られていた。
ジョゼフは、あろうことかその死体袋の脇に鞄を放り、枕にして横になっていた。
アリーセは幌の外、御者席で馬車を進めていた。
道中、車輪の音だけが響いていたが、沈黙に耐えかねた私の質問に、ジョゼフが丁寧に答えてくれた。
彼らは”屍術団”を名乗り、人類の勝利と復興を標榜しているらしかった。
私はつい、随分安直な名だと言ったが、ジョゼフは「俺達にとっちゃ、名前なんてどうでもいいんだよ」と笑った。
屍術師達が集まり、この災禍をもたらした地底の王とやらを屠るために、各地に散在する様々な知識や技術を集め、日夜戦いに耽っているとの事だった。
組織には他にも多数の術士達がいるらしかったが、この3人のように少人数でグループを組み、任務に当たる事が多いとも聞いた。
その日を生きる事ばかりで精一杯の私にとっては、まさに雲の上のような世界だった。
彼らがどれほど恐ろしいものと対峙しているのか、想像する事もできなかった。
ただ、山中で村民が出くわしたような怪異も、彼らにとってはきっと、容易く解決してしまうような日常茶飯事なのだろうなという事は想像できた。
矮小で無力な人間には、自分で自分の未来を決める事すら叶わない。
私のようなただの狩人には、運命は変えられなかった。
己の手で己の運命を決められると信じる彼らの存在は、とても羨ましいと思った。
だから私は、仲間が消え去った山へと登っていく馬車の中でも、不思議と落ち着いている事ができたように思う。

幌の外から馬の嘶きが響き、揺れが収まる。
馬車が目的の野営地に到着したのだ。
私は術士2人を促して先に降りてもらい、続いて地上に降り立つ。
長い時間揺られ続けていたせいか、降り立った直後に軽い目眩を感じ、私は思わず荷台に寄りかかってしまう。
エレドスティを登る道は、ここで途切れている。
車輪で踏み込めるのはここまでで、ここから先の斜面と険しい岩肌は、馬車で立ち入る事はできない。
この窪地の開けた荒れ地は、露出した土中に含まれる塩分のために雪が積もらず、狩人達が夜通し狩りを行う際にも野営のため頻繁に使われていた。
疎らに立った木の陰を見れば、ロープの切れ端や布切れが散見され、過去にここを使った者達の痕跡が確認できた。
おそらくは私自身が最後に山に登ったときに焚いた焚き火の跡もそのまま残されていた。
ライツは窪地に降り立つが早いか、すぐに石灰の白墨で荒れ地の地面に何かの図形を淡々と描き始めた。
アリーセは馬車の荷台と幹の太い手近な木をロープで手早く括り付けると、荷台に積まれたあの忌まわしき袋を次々とライツの描く図形の脇へと降ろし始める。
ジョゼフは、同様に馬車の荷台奥に積まれていたであろう折りたたみ式の椅子を取り出すと、図形の目前に揺れのないようしっかりと固定し、その上に深々と腰を下ろすと、懐中から取り出した帳面を熱心に読み込み始めた。
三者三様に、これから始まる探索に向けた準備を始めていると素人の私にもすぐに判断できた。
一方で、私自身はというと、明確な目的を持って動く3人を前にして所在なげにウロウロと図形の周囲を歩き回っていた。
時折、荷物を運び出す途中のアリーセの通り道を塞いでしまい、舌打ちされ、慌てて脇に避ける場面もあった。
やがて一通りの荷物は出し終えられ、図形を描くライツの手も止まった。
ジョゼフはそれに気づき、帳面を畳み懐中にしまい直すと、両手のひらで顔を2,3度強く打ち付けた後、気合を入れるように言葉にならぬ声を発し、ライツに声をかけた。
「やろうか、リーダー」
「急くな、結界が先だ」
そう答えたライツは、ブツブツとなにかの呪文のようなものを呟き始めた。
間もなく、光の筋がライツの指先から放たれると、窪地の周囲に積もっていた雪がその光を反射して輝き出すと、やがて私の視界はぼやけ始め、窪地全体にまるで靄がかかったかのような景色へと変じた。
「ワットさん。この窪地から外には決して出ないように」
「アンタ一人で死ぬ分には勝手だが、俺らまで見つけられたら困るからな」
ライツの説明を、ジョゼフが物騒な形で補足する。
アリーセは相変わらず無言のまま、腕組みをして山頂の方角を凝視していた。
ジョゼフは腰掛けた椅子の上で胡座をかくと、目を瞑り、頷く。
それを認めたライツが先程とは異なる呪文の詠唱を始める。
地面に描かれた図形が仄かな光を放ち始めると、アリーセが傍らの袋をひとつ軽々と抱えあげて、円形の図の中央に丁寧に横たえ、また元の位置へ帰る。
やがてライツの呪文に呼応するように図形の光は力を強め、やがて袋そのものが発光を始める。
あまりの眩さに、思わず手を翳して光を遮った。
次の瞬間、嘘のように光が去り、ライツの詠唱も途切れた。
ライツは図形の中央に歩み寄ると、袋を固く封じていた紐を丁寧に解いた。
すると、ああ、これがこの、悍ましき屍術師の業だと言うのか。
袋の中から、頬の肉が破れ、奥歯が露出した顔が覗く。
男の死体が、独りでに起き上がり、地面に手をつき、気怠げに立ち上がった。
ボロ布だけを身にまとい、体のあちこちが綻んで皮膚の内に秘めた真紅の筋肉が覗いている。
遡った胃酸が喉を焼いた。
臭いなどはない。
ただ、その悍ましさ、涜神的な情景に、心が悲鳴を上げていた。
「ジョゼフ、行けるか?」
ライツが死体に声をかけている。
当のジョゼフは、椅子の上で項垂れて、返事をしない。
直立した死体の喉がひゅうひゅうと鳴り、軽く咳払いをひとつ、そして地の底から響く呻きじみた声が発せられる。
「いつでもいけるぜ」
これが、今のジョゼフなのだ。
そこで項垂れた青年は今、ここに立つ死した者の身にその心を宿しているのだ。
耐えきれず、私はその場に吐瀉する。
馬車の中で受け取った林檎の残骸が荒れた土に撒かれる。
「おい、しっかりしてくれよ。ここからがアンタの仕事なんだ」
死体が、その見た目に反した軽口を私に向ける。
一見滑稽にすら見える、この世のものとは思えぬ一幕。
脳の奥の方が、急速に痺れて鈍磨していくのを感じる。
死体は、その立ち上がった時とは別人のような軽快な足取りで、早々に靄の結界の外へと駆け出して、そのまま見えなくなった。
ライツがその姿を見届けると、再び呪文を唱え始める。
やがて、靄の中に、鮮明な幻像が浮かび上がってくる。
風のように過ぎ去る山地の景色。
まるで、崖や岩場を駆ける猫科猛獣の瞳に映るものを覗き込むようだ。
やがてその視界は、今我々が立つこの野営地を見下ろす位置で止まる。
「視界、声、問題ないか?」
やまびこのような声が耳の中に響く。
「問題ない。ワットさん、あなたにも彼の視界と声が見聞きできているか?」
ライツの問いは非常に奇妙なものであったが、首肯する以外になかった。
ここからが私の仕事…
たとえ彼らが屍術に精通し恐るべき力を行使できたとしても、この山の地理には不案内なのだ。
だからこそ、この山に精通した案内人を、この山に生きてきた狩人を求めたのか。
震えが止まらない。
もう前に進むしかない。
これを選んだのは、自分だ。
生き残るための代償。
こうして図らずも、私は屍術師達の戦いに巻き込まれる事になった。
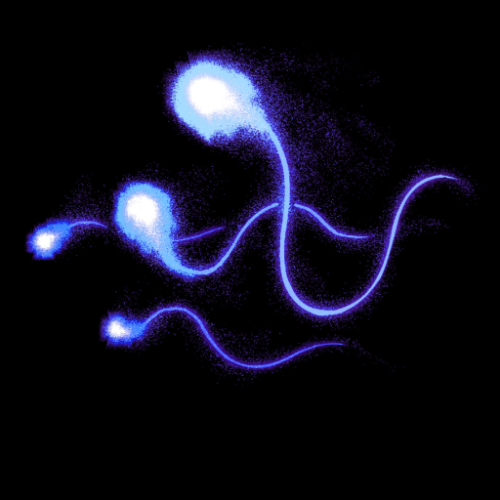
~つづく~
「ショートストーリー」は、Buriedbornesの本編で語られる事のない物語を補完するためのゲーム外コンテンツです。「ショートストーリー」で、よりBuriedbornesの世界を楽しんでいただけましたら幸い
です。





