
その帝国は、一夜にして滅びたと言われている。
あらゆる建造物はそのままに、すべての人間が姿を消した。
やがて他所からその地に流れてきた人間達は、もぬけの殻の都市に残された生活跡だけを目の当たりにしたと言う。
そこに暮らしていた人間達がどこへ行ったのか、知る者はいない。
歴史はやがてその都市を飲み込み、ある地には新しく流れ着いた者達が住まい、またある地は朽ちて地の底に埋もれていった。
誰でも知っている伝承である。
しかし、この伝承には疑問点が多い。
帝国の版図は、地平線の彼方にまで及んだ。
国土を覆う無数の都市や村々から、仮に、本当に一夜にして人だけがいなくなったとして、それを誰がどうやって確認できたというのか?
いなくなった瞬間を目撃した、という記録も残っていない。
噂が伝わるにつれて誇張が繰り返されたのか、そうした誇張を誰かが記して残したのか、確認する術が古代には存在したのか…
少なくとも滅びたとされる都市の遺跡が残っている事は確かであり、噂そのものがただのお伽噺ではない事も示唆されている。
歴史に空いた不自然な空白、ミステリには多くの歴史学者が惹きつけられた。
この伝承が生まれた経緯に何があったのか、多くの歴史学者達は様々な仮説を立てているが、確証に至ったものはない。

帝国の創立者ヴァーニスは、”暴帝”と呼ばれ恐れられた。
力だけが支配する世界を築き上げた皇帝は、より多くの領土を奪ってきた者を優遇し、結果が出せなかった者は容赦なく首を刎ねた。
「俺よりも多くの戦果を挙げられたなら、皇帝の座を譲る」
ヴァーニスは家臣たちに、よくこう告げたと記録されている。
しかし、実際にそれを成し得た者は一人もいなかった。
ヴァーニスには、戦争に必要な全てが備わっていた。
知を駆使し、力を奮い、何より付き従う者の心を掴まえる術に秀でた。
「この男についていけば間違いない」
誰もにそう思わせるだけの天賦の才がヴァーニスにはあった。
イナゴの大群のように領土を広げ、その勢力は留まる事はないかに思われた。

しかし、覇道は志半ばにして途絶える事となる。
赴いた戦地で不治の病を発症し、暴帝は為す術なくこの世を去った。
あまりにも呆気なく、また急過ぎる崩御は、国内に混乱をもたらした。
もはや、侵略どころの騒ぎではなくなった。
ヴァーニスは正妻を持たず、国中のあちこちに妾を囲い、転戦する先々で子を設けた。
そのため、この時の後継者候補は、国中で実に200人を超えていたとされる。
帝国は、瞬く間に内乱状態に陥った。
正統後継者を主張する派閥が無数に乱立し、侵略時代よりも血腥い衝突が国中で起きた。
結果、この蠱毒めいた惨状を征して帝国を統べたのは、意外にも虫も殺せ無さそうなほど柔和な青年、ワーレンだった。
だが、彼こそが後世に”賢帝”と伝えられた、2代目皇帝である。
ヴァーニス帝の没年にはまだ16の齢であった。
彼は、特別に力が強いわけではなかった。
ただ、”本狂い”とも称されるほどの、読書好きであった。
そして何より、男女問わず人を惑わすほどの美男子であった。
彼の、人の心を優位に動かす術は、父のそれすら霞むほどのものであった。
むしろ、そのあまりの人たらしぶりを恐れた臣下達は、陰で「魔性」「蛇蝎帝」とまで呼んだ。
結局彼は、一度として戦場に足を向ける事なく帝位に就く偉業を成し遂げる。
ワーレンは、国を治める術は心得ていた。
ヴァーニス侵略時代ほどの熱狂こそなかったものの、一度は内乱で崩れかかった帝国を立て直し、他国に抗するに足るだけの防備も怠らなかった。
拡大拡張によって帝国民を富ます、さらなる繁栄がなかったという点で言えば満点とは言えないが、それでも及第点ではあったかもしれない。

ワーレン帝の時代は10年も保たずに終わりを告げる。
本当に偶然、ただ階段を踏み外しただけだった。
たまたま、身近に身を支えられる側近がいなかった。
たまたま、手をついた手すりが雨で滑った。
ワーレン帝は、頭を強かに打ち、打ちどころ悪く、そのまま世を去ったと記録されている。
当然暗殺は噂された。
何より、跡を継げる人間がまだ6歳の長女しかいなかった。
摂政を務める事になったロー氏に嫌疑がかけられた。
彼が摂政がついて以後、明らかに国政は荒れた。
贈賄が横行し始め、貧富の差が広まり始めた。
しかし、確たる証拠は出ず、ロー氏が暗殺の件で座を追われる事はなかった。

即位当時6歳だったティアナ女帝の時代は、後に暗黒時代と呼ばれている。
国政への不満が募り、ロー氏の称する「治安維持活動」の革を被った弾圧が国民を苦しめた。
「先帝の意志を継ぐ」という名目で侵略行為が再開されたが、優秀な将兵を欠いた前線は、思うような戦果も上がらず、いたずらに国内資源を浪費し疲弊するばかりであった。
悪化する状況を打破すべく、多くの奴隷が国内に連れて来られた。
しかし、それ自体が国内の治安状況をさらに悪化させる一因にもなっていたかもしれない。
奴隷商が各地に増えたが、満足な警備も持たずに輸送していたため、結果として脱走奴隷が野盗に身をやつすケースが跡を絶たなかったのだ。
帝国民の奴隷に対する印象は劇的に悪化し、ただでさえ強かった差別意識がより一層強まった。
しかし、国内には奴隷自体を排斥する労働余力もなく、避けるに避けれぬ相手に対して、互いに強い憎悪を募らせ合う泥沼に突入していった。

奴隷の子は、奴隷。
奴隷が生み、奴隷が世話をし、奴隷が奴隷に育て上げる。
しかし、この慣習には例外があった。
帝国は、魔術院と呼ばれる、国家直轄の研究組織があった。
帝国において、魔法は様々な分野で役立つ技術として重宝されていた。
しかし、個々人の魔力の総量は先天的なものだった。
また、複雑な魔術の論理を読み解ける者は、たとえ然るべき教育を受けた者の中でも極わずかであった。
帝国に貢献できるほどの才能溢れた魔術師ともなれば、ほんの一握りである。
そのため、たとえ奴隷であっても魔力と知性の才能さえ見出されれば、貴重な人材であるために出自を問わず登用された。
それがまた魔術院内での醜い派閥争いに発展する事もままあったが、それ以上に魔術の才能は貴重であったために、背に腹は代えられなかった。

あるとき、魔石の原料となる水晶を掘り出す鉱山に、魔術院の研究員達が視察に訪れていた。
魔術的手段による採掘効率改善を検討するという名目ではあったが、実際には鉱山を保有する商家が、時代に左右されず一定の権力を有し続けてきた魔術院の有力者に取り入る機会を設けるために準備された、半ば形ばかりの視察であったと記録されている。
研究員達が坑道に足を踏み入れようとしたとき、少年が駆け寄ってきた。
それは、煤に汚れた奴隷の子だった。
研究員達を案内していた商家の主は苦々しそうに手振りで少年に離れるようジェスチャーしたが、少年はじっと研究員達を見て、言った。
「星が笑ってるから、中には入らない方が良いよ」
商家の主は怪訝そうに髭を撫でながら少年に仕事に戻るよう一喝しようとしたが、研究員の一人がそれを止めた。
その男の研究員の目は、真剣そのものだった。
「それは… どういう意味かな?」
研究員が質問しようとした次の瞬間、坑道内から爆音が響き、粉塵が吹き出てきた。
追って、坑道内からは悲鳴と、怒声が混じりながら、血を流す奴隷達が駆け出してきた。
「瓦礫の下敷きになってる!」
「早く、手を貸してくれ!」
砂埃に塗れて騒然とする坑道の前で、その研究員と奴隷の子だけが、互いを見つめ合っていた。
「…今の爆発、星が教えてくれたのかい?」
「ううん、僕が星を見たんだ。空の外側を」
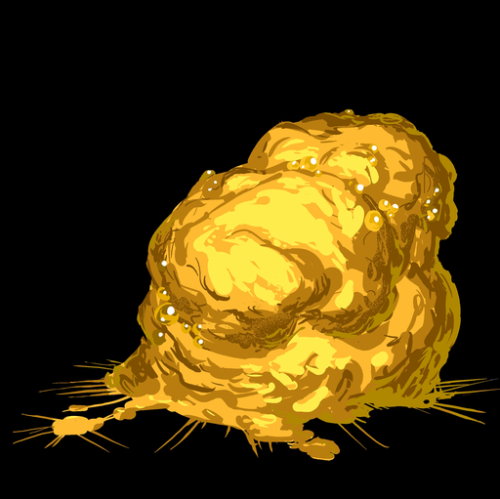
爆発の正体は、復讐を企図した奴隷による単独犯行であった。
普段は訪れない雇い主が、魔術院の視察に合わせて坑道へやってくる。
そこに合わせて、坑道の天井を爆破し、憎き雇い主を生き埋めにする。
いつかの事故で命を落とした、我が子と同じ目に遭わせるために…
犯人もまた、坑道の中で待ち構えていた。
復讐と共に、自身の命も断つために。
少年の言葉が、一団の歩みを止め、計画を狂わせた。
その奴隷は、無関係の仲間達を道連れに、目的も達せず自爆してしまったのだ。
しかし、事件の真相を知る者は、後の世には残されていない。

奴隷の子は、瞳に強い光を宿していた。
その声は、誰にも動かせない意志が宿っていると感じらせた。
魔術院へと帰還する馬車に同乗した彼の姿には、既になにか威容とも言える雰囲気が漂っていた。
生まれながらに天に与えられたもの。
天に立つべき者だけが持つもの。
とても、10歳にもならないような年頃の子とは思えなかった。
伸び放題の黒髪を緩く縛り、垢汚れたボロをまとい、遠くを見据える浅黒い少年。
後の世に”覇王”と呼ばれ畏れられた男が、その日初めて、歴史の表舞台に姿を現した。

彼と対話した研究員は、確信していた。
この子には才能がある、と。
それも、ただの才能ではない。
魔力の強さや、知性だけではない。
この子には、「見えざるものを見る力」がある。
それを、彼は見抜いてた。
この研究員にとって、それは他人のものではなかった。
彼もまた、魔術院の中でさえ数少ない、「見えざるものを見る力」を有する一人だったからだ。
彼は、仲間内から、こう呼ばれていた。
「予言者」と…

~つづく~
「ショートストーリー」は、Buriedbornesの本編で語られる事のない物語を補完するためのゲーム外コンテンツです。「ショートストーリー」で、よりBuriedbornesの世界を楽しんでいただけましたら幸い
です。




