
クリス・ウォーリーがこの町にやってきたのは、数年前の事である。
クリスは生後しばらくは両親と共にあちこちの港を転々としながら、2人の仕事を手伝いながら暮らしていたらしい。
その時期では、生活のほとんどは船上であったとも聞く。
両親を流行り病で亡くすに前後して、彼は伝染を避けるためにも、泣く泣くこの町に移り住む事に決めたらしい。
彼の邸宅には元々彼の伯父であるカール氏が住んでいたが、入れ替わる形でカール氏は町を出て、商売の拠点に港に移したとの事らしい。
それからしばらく、クリス氏はデイティの邸宅に身を落ち着けた。
しかし、多くの町民は、彼の姿を見ることは稀であった。
クリス氏は自宅から外に出る事はほとんどなかったらしい。
必要な用事や買い出しも、ほとんどが召使いのバルトが代行していた。
そのバルトも、町の人々とは言葉が通じなかったため、クリス氏から託されたメモを頼りに用を済ませる、という奇妙なものだった。
町民はバルトを気味悪がったが、それでもクリス氏を尊重する態度は見せていた。
というのも、クリス氏は毎年、町に対して多額の寄付をしていた。
この寄付は目録にも記録が残っており、その額は町でも1,2を争うほどであった。
両親から相続した遺産がどれほどの額であったかを知る者はいなかったが、寄付額から、余程の事がない限り食べていくに困る事もないだろうと想像されていた。
直接語る機会は多くは持たなかったが、たまに顔を見せる時、クリスはいつでも袖の長い外套とフードをまとって、蒼白で、不健康そうに見えた。
体が弱く病気がちで、なかなか外出することもままならないと、事あるごとに町の者達に愚痴をこぼしていたらしい。
自分はこんな状態だからろくに町の活動に参加することもままならない事が本当に申し訳ない、寄付はその代わりだ、と語っていた。
殊勝なことだ、と町の老人達は口々に漏らしていた。

そんなクリス氏ではあったが、唯一足繁く通っていた場所があった。
町の西端、斜面を降りる急な坂を降りた先にある、教会である。
多くの町でそうであるように、かつてはこの教会も王国の制定した国教を司る施設として、半ば町の自治組織の集会場のような役割を担っていた。
しかし、度重なる内乱、王国体制の変革、国外からの難民の流入などを経て、国教遵守の義務は事実上形骸化しており、各地で様々な外来あるいは新興の宗教が蔓延していた。
デイティも例外ではなく、ここ数十年で名も聞かぬような新興宗教が新たに勃興し、町内で勢いを伸ばしていた。
そしてその教会も今では、買い取ったその宗教団体が拠点施設として利用していた。
クリス氏はどうやら、その新興宗教に熱を上げていたらしい、という事が、多くの町民への聞き込みから判明した。
その宗教はいわば一種の終末思想を掲げており、まもなく訪れる破滅の時に、信じる者だけが救われる、あるいは運悪く命を落としたり、大切な人がそのような目に遭っても、信じる者達は蘇る事ができるとすら喧伝していたらしい。
一昔前であればそのような胡散臭い団体は煙たがられ避けられたものだが、デイティにおいては事情が違った。
不安定な情勢や教主の異様な弁舌が町の人々を瞬く間に惹きつけて、信者が多数派に回るまでそれほど時間はかからなかったようである。
そうした事情から、クリス氏がその施設に出入りする事にわざわざ意識を払う者もいなかった。
ただ、生活必需品の買い出しさえ召使いに任せる男が、宗教施設には自らの足で通うのを厭わなかった事は、町民にとっても訝しい点ではあったようだが。
クリス氏の熱心さは折り紙付きであったが、彼がそこまで宗教に入れ込むのも、健康上の問題に起因しているのではないかと噂されていた。
つまり、病魔を、あるいは近く訪れうる死を克服したいという、願望というか、執着のようなものが彼にはあるように思われていたわけだ。
さらに数十年前、この宗教の関係者が町に初めて訪れたとき、布教や理解を広めることに腐心したのが、他ならぬ伯父カールであったという事もわかった。
その経緯は当然、クリス氏がこの宗教に強く入れ込んでいる状況を説明する形にもなっていた。

多額の寄付、疎らな交流によって、特別好意を持たれるわけでもないが、同時にトラブルとも無縁だったはずの彼が、唯一トラブルを起こしていたのが、ウォルターと呼ばれる男性である。
ウォルターはデイティの農夫の息子であり、クリス氏とは同じ年頃の青年だ。
彼は定職につかず、気まぐれに父の手伝いをする事もあったが、多くの場合日がな一日酒を片手に町をぶらぶらするような、半分ごろつきのような輩だった。
そのため、当然のことながら彼の評判はすこぶる悪かった。
それでも周囲が彼を邪険に扱えなかったのは、町に献身的で真面目だった父のおかげと見られる。
あるとき、ヴィルマという若い乙女が彼の目に留まった。
彼女は特別美人というわけではなかったが、愛嬌があり、気立てが良く、友人も多かった。
ヴィルマはウォルターに付きまとわれて、ひどく迷惑していたが、ある時、彼女は言った。
「私は、心に決めた方がいるんです」
それは、男を諦めさせるために咄嗟についた、よくある嘘だったのだろう。
だが、ウォルターは、あろうことかその相手がクリス氏ではないかと勘ぐり始めたのだ。
実際、クリス氏にはそういった噂がなかったわけではなかった。
年頃で、痩身ながら長身で、やや不健康そうな点を除けば憂いを伴った端正な顔立ちは一部の少女達にとって憧れを抱いても不思議はない、と思われるようなものだった。
しかし、クリス氏とヴィルマにはそもそも面識がなく、仮に互いの顔を見知った事があったとしても、逢瀬を重ねるような時間が、ヴィルマの方にそもそもなかった。
だが、恋は盲目とでも言おうか、ウォルターはそうした第三者からの助言にも耳を貸さず、クリス氏に憎悪を募らせていった。
ウォルターは、直接クリス氏の自宅を訪ねては無関係の者も不快になるような猥雑な内容の質問を浴びせたり、外出するクリス氏を尾行したり、様々な嫌がらせをするようになった。
クリス氏自身は、辟易してはいるようだったものの、意に介さず普段通りの生活を過ごそうと努めていた。
そこに来て、ヴィルマが荷馬車に轢かれる事故に遭い、亡くなった。
タイミングとしては、まさに最悪であった。
ウォルターは悲嘆し、そして憎悪をさらに強める事となった。
ヴィルマの葬儀の夜、彼はクリス邸を訪ねて、門前払いを受けながらも、玄関先で思いつく限りのあらゆる罵倒語を並べて、帰っていった。
それからと言うものの、ウォルターは方々に「クリスがヴィルマを殺した」を吹聴し始めた。
周囲は当然、彼の言う事を信じるわけはなかった。
だが、さらにウォルターは「クリスは死んだヴィルマの亡骸を掘り起こして、自分のものにしようとしてる」などとまで言い始めた。
さすがに周囲はこのようなウォルターの発言を咎めた。
愛する人を失った悲しみによって、気が触れてしまったのではないか、とまで言われた。
鬼気迫る彼を恐れて、周囲の人間は徐々に彼に近寄らなくなった。
今回のクリス氏失踪で、当然ながら彼は第一に容疑をかけられていたが、クリス氏失踪の夜、彼が一晩中町のバーで酔いつぶれて眠っていた事を店員と他の客が証言した事で、疑いは晴れたらしい。
また、ウォルターの父へのインタビューでも「あいつに他人をどうこうするような度胸はない」と断じられた。
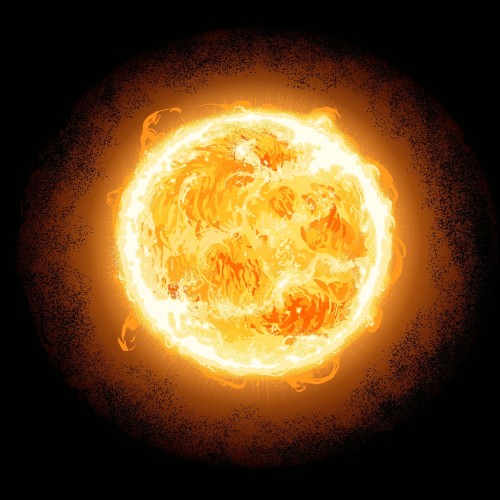
ここまで得られた情報は、全て町に住む多数の住民から得られた証言によって、裏を取る事ができた。
以下が、彼が失踪した日について得られた情報である。
・雲ひとつない、晴れの夜だった。
・クリス氏は夕暮れ時に教会に行った。夜明け前に教会を出ていくところを見た、と証言する者が複数いた。
・クリス邸にクリス氏が戻ってくるところを見た、という者もいた。ひどく疲れて、憔悴しているように見えたらしい。
・その後、クリス氏を見た者はいなかった。
こうなると当然、最後にクリス氏を見たのはバルトという事になるのだが、質問に応じようとするバルトの話す西方の言葉を理解できる者が町内にいなかった。ただ、カール氏がクリス氏の残した衣類と身振り手振りとでバルトに質問の意図を伝えようとしたところ、寂しそうな顔をして、玄関を指差しただけだったそうだ。

教会でのインタビューは、また要領を得ないものだった。
私を出迎えたのは、教主のアロイスという小柄な男だった。
曰く、彼はこの教会に来てから2代目の教主で、数十年前に町へやってきたとき、先代教主に拾われた孤児だったらしい。
まだ30代後半と若かったが、そうとは思えぬほどに老け込み、老成してすら見える様子は、ある意味では教主らしい風格を携えている、教主に相応しい人物のようにも見えた。
彼は部外者に対して強く警戒心を持っている様子だったが、クリス氏の捜索の旨を伝えたところ、快く調査協力に応じてくれた。
曰く、クリス氏は町だけでなくこの教会に対しても惜しみない寄付を行っていたらしい。
そしてそれは、カール氏もまた、同様であった事も知る事ができた。
失踪した夜に何があったかを尋ねたが、それについては、やはり要領を得ない結果となった。
クリス氏はいつものように教会を訪れ、アロイス教主と少し言葉をかわした後、ずっと礼拝堂に一人でいたとの事だった。
祈っていたのであろう、とアロイス教主は言うが、実際に見たというわけでもないらしい。
アロイス教主自身は、やはり一人で、教会奥の寝室で遅くまで読書し、その後床についたとの事だった。
それは静かな夜でしたよ、とも答えた。
突然いなくなるなんて、そんな予兆は微塵もなかったのに、とアロイスは残念そうに語った。

「…結局、何故いなくなったのかも、その後足取りも全くつかめなかったってわけか」
「相変わらず飲み込みが早いですなぁ、ドミニク殿は」
ドミニクとシュンは、橋のたもとで落ち合っていた。
「それじゃあ、どうすんだ?絶対見つけるなんて啖呵切っちまったんだろ?」
「もう見つけましたよ、クリス氏は」
「なんだと!?」
手すりに腰掛けていたドミニクは立ち上がりながら怒鳴った。
「大きな声を出さないでください…」
「まず説明をしろと言ってるんだ。お前は毎度毎度、一人合点してばっかで何も説明しやがらない。わかってる事があれば、こっちだって動ける事、やりようが色々あるんだ。とにかくちゃんと話せ」
「…すみません、ドミニク殿の言う通りですね。ただですね、私の中でも、確実な事と不確実な事がまだ無い混ぜの状態で、下手に説明すれば混乱させるかもしれない、と思いまして」
「何も説明されないよりマシだ」
シュンは大きなため息をついて、観念したように口を開いた。
「クリス氏はまだ、あの屋敷にいます」

~つづく~
「ショートストーリー」は、Buriedbornesの本編で語られる事のない物語を補完するためのゲーム外コンテンツです。「ショートストーリー」で、よりBuriedbornesの世界を楽しんでいただけましたら幸い
です。




